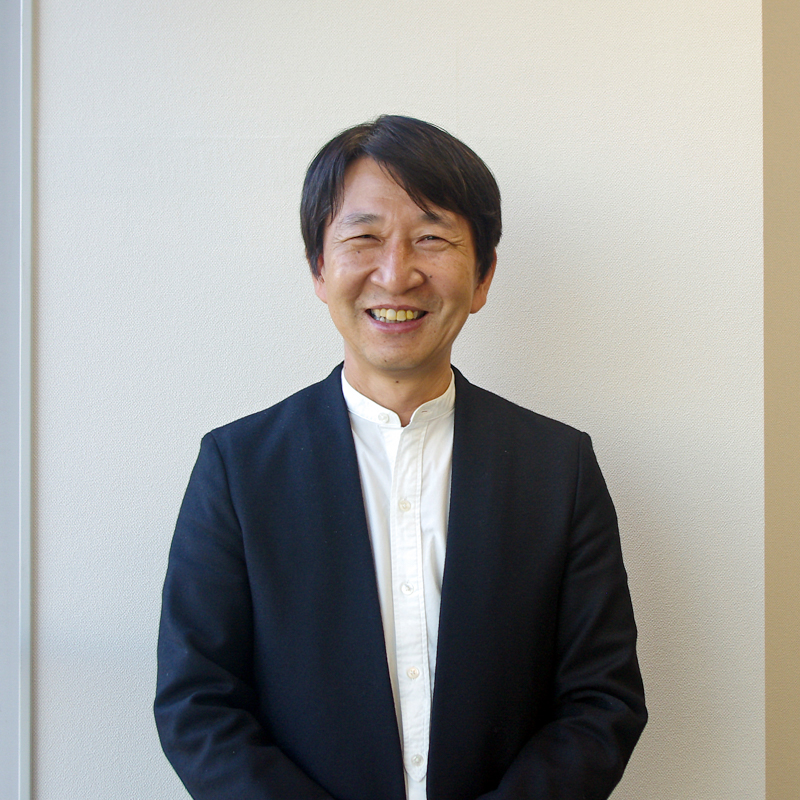自分の言葉を、誰かの言葉に。受け継がれる歌を、歌い続けたい。
ミュージシャン
安岡 優さん
男性ヴォーカルグループ、ゴスペラーズのメンバーとして1994年にメジャーデビュー。「永遠(とわ)に」「ひとり」「ミモザ」といったロングセラーを記録する傍ら、多くのアーティストの楽曲に作詩家として参加。その他、映画エッセイ本「架空の主題歌」を出版するなど、多才な活動を展開している。
https://www.gospellers.tv/
日本におけるアカペラの認知度を一気に高めたヴォーカルグループ、ゴスペラーズ。2019年にデビュー25周年を迎え、チャリティコンサートも積極的に開催しています。メンバーの中でも安岡 優(ゆたか)さんは精力的にボランティア活動に参加し、ジョイセフの活動を支援してくださっています。ボランティア活動や女性と子どもの支援などに関する考えと、ご自身の生業である歌を通じて、自分らしく生きることの大切さについて伺いました。
チャリティコンサートで学んだ、お母さんたちが喜んでくれるということ
安岡さんがチャリティ活動に参加するようになったきっかけを教えてください。
ゴスペラーズの母校である早稲田大学には、2002年から平山郁夫記念ボランティアセンター(以下、WAVOC)があって、学校ぐるみで国内外における学生のボランティア活動を支援してきました。それで、僕たちも歌を活かして、WAVOCを通したチャリティ活動をしていたんです。
最初の訪問先は、佐賀県にある加唐島(かからじま)という離島。本土と島をつなぐフェリーは最終便の時間が早いので、大人になって島を離れるまでライブやコンサートなど、生の音楽に触れることができないそうです。ならば、コンサートをやる僕らから出かけていけばいいじゃないか、と考えて、そのためのスタッフの旅費などを募るチャリティライブを早稲田大学で開きました。
早稲田大学はチャリティの意識が高い校風なんですね。
早稲田には多くの学生音楽サークルもありますから、自分たちが旗振り役になって、みんなで歌が届きにくい街に歌を届けよう、できるだけ楽器を使わないアコースティックな構成で届けていこう、という考えでしたね。
その後、ゴスペラーズは東日本大震災の被災地でもボランティア活動を行っています。
ゴスペラーズは2011年5月には被災地に向かって、避難所や公民館、学校や病院などで歌い始めました。早稲田からも多くの学生たちが音楽だけでなく、子どもたちに勉強を教えたり、一緒に遊んだり、泥出しなどの作業を手伝ったりと、さまざまなボランティア活動をしました。それに対して、大学側が被災地までの移動手段としてバスを提供したり、全国にいらっしゃるOBOGのネットワークを駆使してボランティア活動や支援物資の受け入れ環境を整えたりしていました。
当時、ジョイセフは国内からより先に海外のプロジェクト地域から日本の被災地への義援金をいただき、初めての国内支援活動を開始したばかりでした。私たちはこれまで、多くの途上国で母子支援に取り組んできましたが、日本でも母子への支援は後回しにされがちな点は海外と同じでした。
東日本大震災では、僕も他の多くの人たちと同じように、ただニュースを見て、情報を調べて、現状を見守ることしかできませんでした。そんななか、「震災の最中にも赤ちゃんが生まれた」というニュースを見たんです。あまりにも大きな災害時でも新たな命が生まれる。命ってすごい、母親ってすごいなと感じました。
チャリティコンサートである中学校を訪問したとき、生徒たちのほかに地域のお母さんたちも観に来ていたのですが、生徒たちが体育館を出た後で、「じゃあ、お母さんたちとも一緒に写真を撮りましょう」と声をかけると、それこそ子どものように喜んでくれたんです。
被災してからお母さんたちも耐えてきたからこその喜びだったのでしょうね。
お母さんたちは子どもたちに「いろいろ我慢しなさい」と言ってきたのでしょうが、一番我慢していたのは、きっとお母さんたちだったんですね。被災しても、男性は仕事に出たりして、避難所にずっととどまることはあまりありません。子どもたちも学校が再開すれば登校します。でも、お母さんたちは避難所から一歩も出ることがない。外の世界に触れる機会が一番少ないのがお母さんたちなんだ、と被災地で聞きました。そのお母さんたちが笑顔になってくれれば、子どもたちにも笑顔が届くはずです。


僕らは医者になれないから、歌で誰かの役に立ちたい
歌というのは、アーティストだからこそできる支援ですね。
自分たちの持っている知識を社会のために活かすのは、早稲田大学の建学の精神です。でも、東日本大震災の後は、あらゆるミュージシャンが無力感に打ちひしがれていたと思います。ミュージシャンの持つ技術や知識は音楽しかない。食料の提供も、労働力も、「ミュージシャンだからできること」ではありませんでした。でも、何をしたらいいかわからないという状況が数カ月続いた後で、被災地を訪れた僕らが歌ったら、それまで楽しいことを我慢していた人たちが、喜びの感情を思い出してくれるのがわかったんです。
被災地を訪れたとき、地元のお医者さんに、「男が5人も揃ってやってきたのだから、労働力として使ってもらったほうがお役に立てるんじゃないですか」と聞いたことがあります。でも、その方がおっしゃるには、「あなた方が医者になれないように、私たちも歌手にはなれない。職業ごとにそれぞれできることがあって、自分のできることをやってもらうほうが大切ですよ」と。その言葉が胸に響いて、少しでも多くの場所で歌うようにしています。
2018年の西日本豪雨では、個人的に泥出しのボランティアもされたと伺いました。
友人が広島県三原市に派遣されたのですが、アクセスが悪くてボランティアさんが足りなかったので、夏休みを使って1泊2日で現地入りしました。現場では僕が発信するだけじゃなく、いくらでも写真を撮ってSNSで共有してもらっていいので、皆さんでどんどん発信してください、という形をとって泥出し作業をしていました。三原市では宿がとれなくて、隣の竹原市に泊まったのですが、そこで夕食をとっていたら、そばにいた人に「県外から来た方ですか?」と聞かれました。「三原にボランティアに来ました。竹原も大変では?」と聞くと、「竹原にはまだ人が来るから、三原に行ってあげて」と言われるくらい、三原には人が来ていませんでしたね。

自分が死んでも、僕の詩は受け継がれていく
安岡さんにとって、チャリティやボランティア活動はどのような位置づけなのですか?
学校で「このカードを買うと、売上の一部がユニセフに寄付されます」っていうキャンペーンが定期的にありますよね。小さいころ、僕の母はそうしたキャンペーンへの参加を促してくれていたんです。だから、誰かのために行動するというのは、自然に身についていました。
大学に入ってデビューしたとき、新人の僕たちは多くの先輩たちに助けていただきました。その方々から受け取ったご恩を、後輩たちに返したいと思っています。英語で言う「Pay Forward」、日本語では「恩送り」と言われる感覚ですね。母の教えも、同じように誰かにお返ししていきたいという気持ちがあります。
ミュージシャンである安岡さんにとっては、いわば自分らしく表現することがお仕事です。でも、若い人たちのなかには自信を持ち、自分の意見を言うことができない人がいるのではないかと思います。
「自分の未来は自分で決められる」ということを、強く信じてほしいですね。僕は大学2年のときにミュージシャンとしてデビューしたのですが、両親には反対されました。そんなことをさせるために早稲田まで行かせたのではない、と。大学に通ってミュージシャンになると言うのは、世間一般でいう普通、当たり前ではないということは重々承知していました。それでも、「自分の未来は自分で選んで決めるんだ」と覚悟を決めて、まずはデビューまでの道筋をしっかり整えて、デビューしてから両親に報告したんです。
ご両親は何とおっしゃっていましたか?
最終的には、父が「お前も20歳になったのだから、自分の職業は自分で決める権利がある。それだけで生活していけないかもしれないという覚悟があるのなら、自由にしなさい。でも、プロになったのだから、自分の面倒は自分でみなさい」と、経済的な自立を条件にミュージシャンの道を認めてくれました。ただ、自分で決めた限り、そこには責任が伴います。
ミュージシャン生活を通じて、どんなことを実感してきたのでしょうか。
僕は25年間、歌い手と作詩家をやってきて実感していますが、言葉を発信するのは怖い作業でもあります。一度リリースした曲の歌詩はもう戻せません。だから、自分の言葉が誰かを傷つけることはないか、この表現は大丈夫だろうか、と念入りに推敲してからでないと、リリースするのは怖いんです。今はSNSなどで自分の意見を発信しやすくなりましたが、その言葉は発信してしまうと二度と消えないということも、若い人たちには覚えていてほしいですね。
それでも、リリースすることには喜びがあります。自分の心の中で思ったことを歌詩にして発信し、誰かに届いたら、それはその人の歌になります。自分だけの言葉だったものが、たとえ自分が死んだ後も残って、受け継がれていく。だから、発信とは喜びにつながるべきことで、責任が伴うことでもあるのだと、心に刻んでいます。

シンデレラが幸せになれたのは、一歩を踏み出せたから
ゴスペラーズの代表曲に「ミモザ」と題されたものがありますね。イタリアでは、「世界女性デー」(3月8日)にミモザの花を贈る習慣があるそうです。
ミモザはヨーロッパでは春を告げる花で、日本でいうと梅に近い存在でしょうか。冬の暗くて色のない生活のなかで、鮮やかな黄色い花が森を彩ると春が来たと実感できるんです。南仏の「ミモザ祭り」なども有名ですよね。
曲の中には、初恋のイメージを重ねて、その記憶を共有できるのは、長い時間を一緒に過ごした二人だけなんだ、という気持ちを込めました。日本ではミモザというと花よりカクテルのほうが有名かもしれませんが、ほっそりとしたフリュートグラスに注がれたミモザ色のカクテルの様子が、シンデレラの靴のようだというイメージも重ねました。
どういうことですか?
シンデレラは、継母に「夢を見てはいけない」と教えられたけど、自分にも舞踏会に行く権利があるんだと信じて一歩を踏み出したから、ハッピーエンドを迎えられたわけですよね。勇気を持って一歩を踏み出すことができれば、どんな境遇からでもシンデレラストーリーは待っていると思います。シンデレラが世界で女性の夢物語として愛されているのも、それが理由じゃないでしょうか。
女性には母親になっても夢を見続けてほしいと思いますし、僕らミュージシャンが発信する曲を、夢にかける魔法のように使ってほしいですね。僕らの曲を聴いているとき、女性たちは少女の顔になっていると思います。ラブソングには、そういう力がありますよ。

男女問わず、若い人たちに届けたいメッセージはありますか?
今は男性だから、女性だからという時代ではありません。男性も、「女性がやるのが当たり前」だと考えていることを、自分でやってみると面白いんじゃないでしょうか。「女性に任せておけばいい」と思い込んでいることをやってみると、どれほどお互いに協力しあって生きているかを実感できるはずです。
安岡さんの中で思い当たる経験はありますか?
僕の世代は中学で、男子は技術、女子は家庭科と分けられていて、そのせいで「男はこれをする、女はあれをする」という思い込みが生まれてしまいがちでした。でも、もうそんな時代は終わったと思いますし、僕は母から裁縫や家事を教えてもらっていたんです。そのおかげで、他人に感謝する気持ちも学べた気がします。今の仕事でも、数多くのスタッフにさまざまなサポートをしていただくのですが、それはすごいことなんだと、子どもながらに実感できたんですね。
男子も家庭の仕事を経験することで、毎日の食事、清潔で整った服などの日常に感謝できる人に育つのではないかと思います。もちろん、男性と女性には違う部分がありますから、時には男性としてすべきこともあるでしょう。それでも、性別による違いよりも、同じ人間として分け合っている時間の方が長いですよ。
私たち大人が知識を分け合うために発信していかなければいけませんね。
そうですね。未熟な若い人がいても大人が知識を伝えなかったせいですから、それを責めるのは違います。体験を通して理解できること、男女が分かり合えることは、たくさんあると思います。
取材・文:I LADY.編集部
編集:加藤将太
*この記事は2019年11月22日に取材したものです