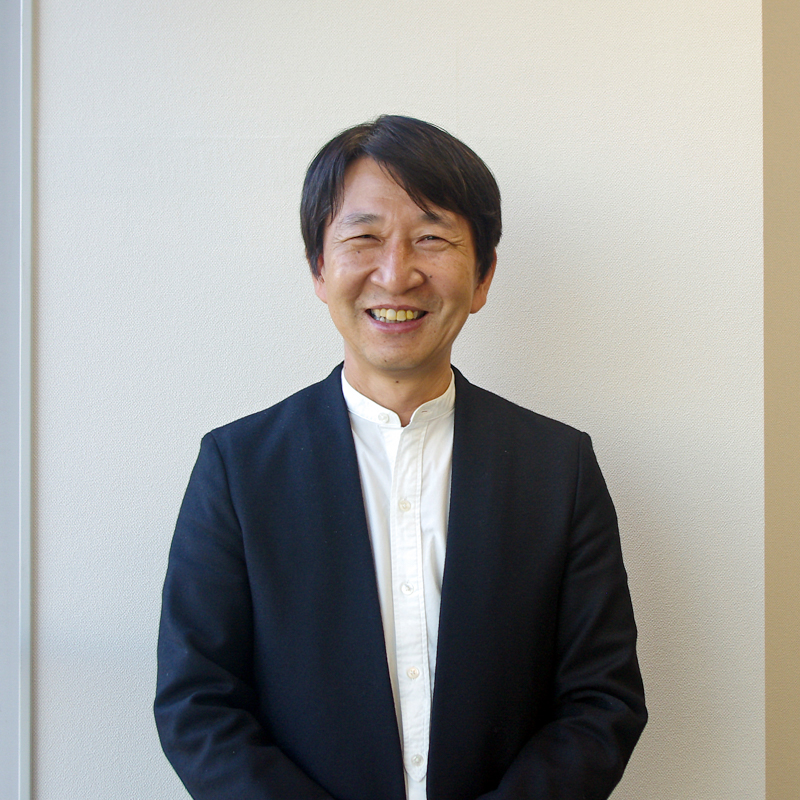「幸せ」は人にしてもらうものではなく、 自分でなるもの
『Numéro Tokyo』編集長
田中杏子さん
ミラノに渡りファッションを学んだ後、第一線で活躍するファッション・エディターのもとで、スタイリストとして雑誌・広告制作などに携わる。帰国後は『流行通信』や『ELLE JAPON』の契約スタイリストを経て、『VOGUE NIPPON』創刊時より編集スタッフとして参加。資生堂「Maquillage」キャンペーンのファッション・ディレクターを兼務するなど多方面で活躍。2005年より『Numéro TOKYO』編集長を務めている。
ファッション・エディターとして、日本のファッション業界の第一人者として活躍し続ける田中杏子さん。そのキャリアは高校卒業と同時にスタートしました。ファッションを学ぶためにイタリア・ミラノに留学し、現地でスタイリストとしてのキャリアを開拓。日本に帰国後は『ELLE JAPON』の専属スタイリストや『VOGUE NIPPON』(現VOGUE JAPAN)」の編集者を経て、『Numéro Tokyo』の編集長に。田中さんがモードの世界を通じて感じてきたフェミニズムの変化とは?ご自身のキャリアの変遷を交えて語っていただきました。
無給が条件でも、イタリアでスタイリストになりたかった
田中さんはファッションを学ぶために、今のキャリアの原点となるイタリア留学を高校生のときに決断したそうですね。既に10代の頃には、スタイリストや編集者になるというビジョンを描けていたのですか?
子どもの頃からファッションが大好きだったので、「大人になったらファッション関係の仕事で食べていきたい」というのは漠然と思っていましたね。将来は自立して、自分でお金を稼いで、人生を切り開いていきたいとも思っていたので、一体どうやったらそういうキャリアを積み上げて生きていけるのかなということもずっと考えていました。それで、このまま日本の大学へ進学するのは何かが違うと感じて、ファッションの勉強のためにイタリアへの留学を決意したんです。
イタリアではどのようなことを学んでいたのですか?
2つの学校でデザインとパターンの勉強をしたのですが、それでわかったのは、私にはデザイナーの才能がないということ(笑)。その自覚をしたとき改めて、中学生の頃から憧れていたスタイリストになりたいと思ったんです。モデルに服を着せて、自分らしい世界観やスタイルを表現する仕事がしたいと。

その後、どのような経緯でスタイリストになる夢を実現させたのか教えてください。
当時のイタリアには、スタイリストになるための学校がなかったんですね。失業率もすごく高い時代だったから、仕事も簡単に見つかるわけではなくて。それで、スタイリストになるにはどうしたらいいかと半年ぐらい模索して、自分の作品を撮影したものを集めたブックをつくることにしたんです。そのブックを持って、いろいろなスタイリスト事務所へ営業に回りました。
そしてやっと、ある事務所に声をかけてもらうことができて、アシスタントとして働けるようになったんです。最初は「無給」が条件だったけど、そのときの私はとにかくキャリアが欲しかったので、全然気になりませんでした。
夢を叶えることへの強い意志があったからこそだと思いますが、「無給でもいいから働こう」というのは、とても思い切りのある決断ですね。
好きなことに一生懸命打ち込んでさえいれば、お金なんて後からついてくると思ってましたから(笑)。実際、最初の1カ月はノーギャラのはずだったのに、4人のボスが「とてもよく働いてくれたから、あなたにお金を支払いたい」と言ってくれて、ポケットマネーから1人約1万円ずつ渡してくれたんです。そのときはもう、すごく嬉しかったですね。
スタイリスト事務所としては、想像を上回る働きぶりだったんですね。
その翌月からは、ちゃんとお給料をいただける契約をしてもらえることになりました。次第に、仕事ができる日本人アシスタントがいるという噂が広まって、アメリカやイギリスの雑誌からも指名されるようになりました。日本人って真面目に働くから、どこでも重宝がられるんですよ。自分のページをやらせてもらう機会も増えていったんですけど、あるとき気が付いたんですよね。「私、日本人なのに東京を知らない」って(笑)。
生まれた大阪からそのままイタリアに来てしまったので、イタリアで東京のことが話題になるたび、東京を知らないことにとても驚かれました。それで24歳ぐらいのときに、東京でも一度は経験を積もうと思って日本に帰ることを決めたんです。ただ、東京のファッション業界には知り合いがいなかったので、また1から営業を始めなければいけませんでしたが。
10代の頃と同じように、大胆な決断力と行動力で人生を切り開いてきたんですね。
これまでずっとそうです。フリーランスのスタイリストから、正社員として『VOGUE NIPPON』(現VOGUE JAPAN)の編集者に転向する際も、それまで築いてきたキャリアやネットワークをゼロにするわけですから、かなり迷いましたよ。でも、その経験があったから、『Numéro Tokyo』の編集長という今がある。 さらに、キャリアを失わずに出産も子育ても実現できました。これまで自分が望んだことはある意味、全て叶えられています。それは自分の可能性を信じて生きてきたからこそだと思います。


自由と平等を目指す、新しい時代のフェミニズム
2017年9月の『Numéro Tokyo』のオンラインマガジンに掲載されていた、「新・女子力とは?」と「新・フェミニズム」をテーマにした記事を拝読しました。そこに書かれていた、「一歩踏み出す勇気、それこそが『新・女子力』」や、「ジェンダーの縛りを超えて、自分らしく生きる勇気」という言葉は、まさにI LADY.が発信していきたいメッセージとリンクしています。改めて、田中さんが考えるフェミニズムについての意見をお聞かせください。
これまで、フェミニストやフェミニズムという言葉を聞くと、男性や社会に対して怒りしか言わないネガティブなイメージがありましたよね。女性の立場や権利を守らなきゃいけないという気持ちが強すぎて、極端に偏った考えになってしまう。そういう一部のフェミニストの人たちは、結果、男性に対抗しようとして自ら女性を否定してしまっています。でも、女性って本当は、もっとしなやかに生きるべきだと思うんですよ。
どういうことですか?
美味しいものを食べて、恋愛をして、綺麗になって、女性であることを大いに謳歌していい。それと同時に、男性へのリスペクトの気持ちも持つ。やはり、男性にしかできないこと、女性にしかできないことというのは存在しますから、それぞれの役割を理解して、一緒に社会を築いていこうという意識でないと。女性も男性もLGBTも、皆が社会の一員です。だから、男性やLGBTの人たちとともに自由と平等を目指す。これが、新しい時代のフェミニズムだと思っています。

『Numéro Tokyo』をはじめとしたファッション誌が新しいフェミニズムを発信することで、日本でもより女性がエンパワーできるための活動が広まっていけばよいのですが。
ファッション業界というのは女性がいないと成り立たない世界なので、男性、女性を問わず、フェミニストの人がとても多いんです。そういう業界が地道に声を上げ続けてきたことで、やっとここまでフェミニズムが広まってきたなという実感はありますね。最近では、<クリスチャン・ディオール>が2017年春夏のパリコレクションで、「WE SHOULD ALL BE FEMINISTS」と書かれたTシャツを発表したことが、とても大きな衝撃でした。
海外と比較すると、日本はどうでしょうか。
まだまだですね。ファッション業界ですら、男性社会が根強く残っている。だから、メディアとして、ファッションを通じてフェミニズムをおしゃれに表現することで、「フェミニズムに対してサポーティブになることは素晴らしいことなんだ」という意識になってもらえれば嬉しいですね。
最後に、これから人生を切り開いていこうとする女性たちに向けてメッセージをお願いします。
日本では、女性が社会に出て活躍するなんて幻想だと思われていた時代がありました。だから、誰かに属したり、依存したりしないと生きていけない女性がたくさんいた。でも、今の時代はもうそうじゃないですよね。仕事でキャリアを築くこともできるし、子どもを持つか持たないかも自分で決められる。もちろん専業主婦になったっていい。選択肢はいくらでもあります。
なのに、選択することを放棄して、誰かに幸せにしてもらおうと考えているなら、それは最初から自分の可能性を否定していることになります。これからの時代、そういう他力本願や依存体質では幸せにはなれません。幸せは人にしてもらうものではなく、自分でなるものなんです。だから、人生の大事な決断を誰かに委ねるようなことはせず、自分で責任を持って選ぶという作業を決して怠らないでほしいです。
取材・文:君島友喜
編集:加藤将太
*この記事は2017年10月26日に取材したものです